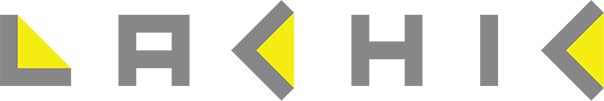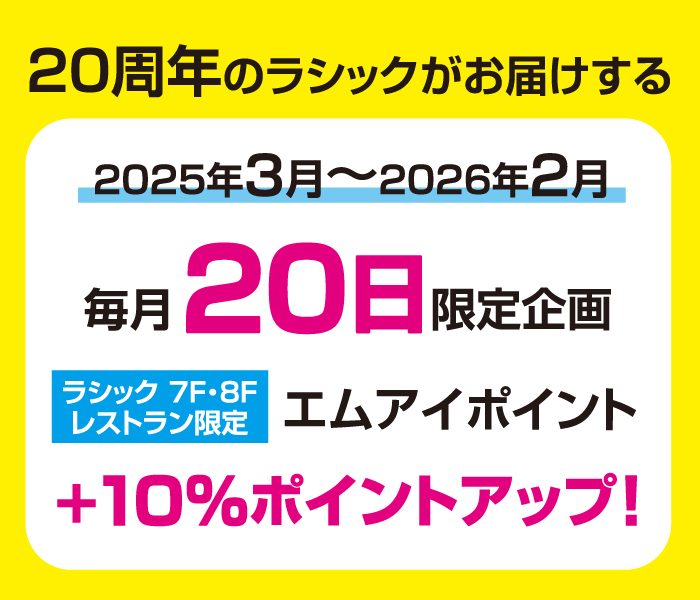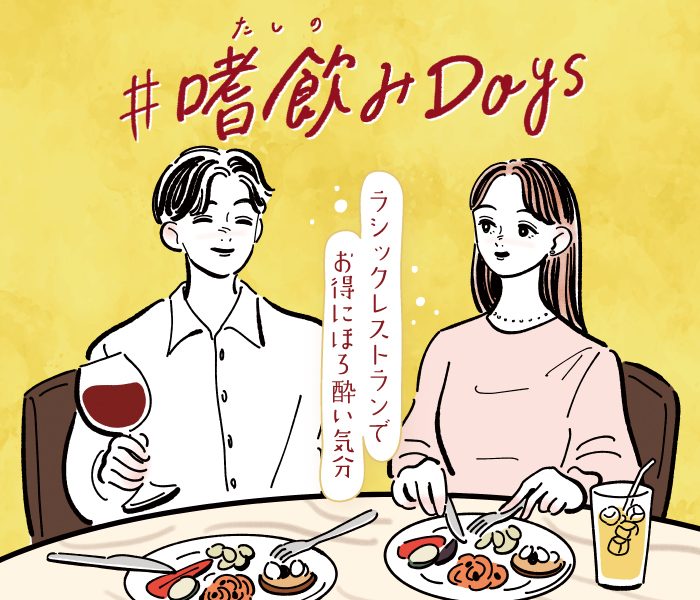もっと新潟のお酒を好きになる
新潟酒フェス@LACHIC
新潟県内でも評価が高い蔵元20蔵がラシックパサージュに!
酒蔵との交流を通じて「もっと新潟のお酒を好きに」をテーマに
100銘柄以上の日本酒を飲み比べ!
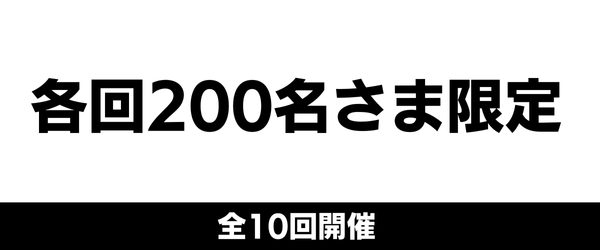
6月6日(金)
①16:15-17:45 ②18:15-19:45
6月7日(土)・8日(日)
①11:15-12:45 ②13:15-14:45
③15:15-16:45 ④17:15-18:45


チケットぴあ(Pコード:657-072)
・セブン-イレブン店内端末「マルチコピー機」
・インターネット予約
http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2518532
※ここから先はチケットぴあサイトです。
※会期中は会場でもチケットを販売いたします。
【注意事項】
各部開演時間から90分間の完全入れ替え制となります。
※20歳未満は日本酒の試飲・購入不可となっております。
※飲酒運転および20歳未満の飲酒は固く禁じられています。
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
※20歳未満の飲酒防止のため、スタッフが年齢確認をさせていただく場合がございます。
※衛生管理上の理由から、飲食物の持ち込みはご遠慮ください。
出店酒蔵のご紹介
「新潟酒フェス」に出店する各酒蔵をご紹介!
※諸般の事情により出店者が変更となる場合がございます。
葵酒造

蔵の始まりは江戸時代、安政年間(1854~1860年)と伝えられ、160年以上前に遡ります。長岡の地で長く酒造りを行ってきた煉瓦造りの酒蔵は大正時代につくられたもので、国の登録有形文化財に指定されています。長岡を意味する「長陵」を主要銘柄に持ち、地域に寄り添った酒を醸してきたこれまでの蔵の歴史を、2024年から新しいチームが受け継ぎました。 長岡から日本全国、更に海外へ目を向け、人々の心に響く日本酒を醸す。脈々と続いてきた日本酒の文化に、今の時代にあった観点を加えていく。私たちは、酒造りという営みを通して、地域の皆様と共に、この地をいっそう面白く、古きを知る新しい酒蔵を目指していきます。
今代司酒造

1767年創業。湊町・にいがたの全量純米仕込みの酒蔵。
古くから酒、味噌、納豆、醤油などの発酵食製造業が集まる「沼垂(ぬったり)」に位置します。江戸から明治時代に栄えた湊町 新潟の風情を残す酒蔵は見学もでき、日本の伝統である酒造りの世界を今に伝えております。
2006年からアルコール添加を一切行わない全量純米仕込みに切り替えました。
純米の旨味とキレの良さの両立を実現することで、食を引き立たせ、飲み飽きせず、人に寄り添える酒造りに努めています。
新潟駅から歩いていける酒蔵として酒蔵見学を年中無休で開催しております。
日本一の蔵元数を誇る新潟県内において、玄関口である新潟駅から最も近くに蔵を構えていますが、酒蔵を閉ざすのではなく、オープンにすることで、少しでも多くの方々がよりいっそう地酒に親しめる環境をご提供することに使命を感じ、日々皆さまをお迎えしております。
越後鶴亀

明治23年創業。新潟市の中心部から車で約1時間、角田山という山麓の町の中にあります。
人々に喜ばれる美味しい酒を目指し、銘も分かりやすく、おめでたい商標をと思い「鶴亀」という名をつけました。
四季折々のハレの日に「鶴亀」という銘柄が非常におめでたいと喜ばれており、父の日・敬老の日、諸所のお祝いにご利用いただいております。
当蔵はお客さまに満足いただける最高酒質を求め、敢えて小仕込みにこだわります。米の選定から適切な洗米条件、最適な吸水条件をその都度設定し熟練の技を駆使して原料米の特性を引き出しています。
菊水酒造

KIKUSUI蔵GARDEN。2025年4月29日(火・祝)グランドオープン!
ここは発酵の奥深さをたのしむ場所。
日本酒は、米と水、酵母と麹が混ざりあい発酵することでうまれます。
お互いが作用して、新たな価値をうみだす。
そうした発酵のもつ魅力を伝えていき、発酵がもたらす気づきや学び、ここちよさ、おもしろさをいっしょにたのしみたい。
発酵をエンターテインメントに。
発酵って、ワクワク。
そう感じてもらえる場所にしたい菊水酒造です。
君の井酒造

創業1842年。蔵に生息する天然の乳酸菌を育む昔ながらの「山廃仕込」の酒を造る数少ない蔵元。雪国新潟でも有数の豪雪地妙高に位置し、この豪雪がもたらす豊かな自然と豊富な地下水、良質な米を贅沢に使用し、伝統の酒造りを継承しています。全てはその旨味のために。惜しみなく手をかけ類稀なる旨味を追求し、お客さまの記憶に残る酒造りに挑戦しています。お酒は旨味豊かで懐が深く、和食だけでなく幅広い食と一緒にお愉しみいただけます。
頚城酒造

人と人をつなげる。料理と人をつなげる。故郷と人をつなげる。幸せと人をつなげる。そして、故郷を未来につなげる。
真の柿崎地酒を造り、感動の食中酒をみなさまに
提供することで故郷を守り、故郷を未来につなげる酒蔵を、<頚城酒造>は目指します。
笹祝酒造

新潟市に所在する明治32年創業の日本酒蔵です。全量新潟市産米を使用し製造量の9割が県内消費であることから「地酒の中の地酒」と呼ばれています。
昔ながらの地域で愛飲される日常酒を造る傍ら新しい飲み手の方にも親しんでいただけるようなチャレンジングなお酒造りも毎年行っており、瓶内二次発酵のスパークリング日本酒やハイボール専用の清酒など、日本酒をより楽しく飲めるような取り組みや商品展開に力を入れています。
酒蔵の建屋は創業以来の木造建築であり、今後国の登録有形文化財に指定される見込みです。
白瀧酒造

<白瀧酒造>の始まりは約170年前の安政2年(1855年)。
初代当主となる湊屋藤助は、日本屈指の豪雪地帯である越後湯沢に涌く、豊富な清水を使って酒造りを始めました。冬に積もった雪は、清冽な雪どけ水となって地面に染み込み、<白瀧酒造>の仕込水として使用されます。
代表銘柄である「上善如水」は、中国の老子の言葉「最上の生き方は水のようである」に由来しており、私たち<白瀧酒造>は、柔軟でしなやかな姿勢で、水のようにピュアな酒造りを目指しています。170年の酒造りの歴史と、自然豊かな酒どころ新潟の恵みを受け、今後も真摯に酒造りに取り組んでいきます。
上越酒造

<上越酒造>は、1804年に創業し220年以上続く酒蔵です。
「無濾過」「瓶燗1回火入」にこだわり、瓶詰後はマイナス5度の冷凍庫で保管しており、いつでもフレッシュなお酒をご提供することが可能です。
また、「人に寄り添う酒造りを」をモットーに、銘柄【越後美人】【越の若竹】を醸造し、より多くの人に受け入れてもらえる親しい友のような、人の心に寄り添うお酒をこれからも造り続けます。
超甘口のお酒など、一風変わった商品を取り揃えておりますので、ぜひ一度お召しあがりください。
高野酒造

<高野酒造>は明治32年9月8日二十四節気の白露(はくろ)の日に創業いたしました。
蔵は新潟市の西部に位置し、冬には日本海からの風雪が大変厳しい地です。
その厳しい環境は酒造りに大変に適しており、120年以上地元で愛される地酒を醸してきました。
蔵の前には広大な越後平野が広がっており、全国有数の米の産地です。原料米の多くは地元農家と直接契約を結び、上質で安心な酒造りを追求しております。
また日本酒に欠かせない「酵母菌」、高野酒造では定番酒の多くに蔵独自のオリジナル酵母を使用し、蔵独自の味わいと香りを醸しています。
近年はリキュールにも力を入れており、皆さまに喜ばれる酒造りを目指しております。
津南醸造

<津南醸造>は日本有数の豪雪地帯である新潟県津南町の秘境・秋山郷の入り口に位置しています。津南町は国内トップクラスの積雪を誇り、雪中蔵での造り、雪解けの仕込水など雪の恵みを活かした酒造りをしています。
雪解け水からなる超軟水の仕込水と雪の降る季節のみの雪中造りにこだわって酒造りをしており、地元の酒米を100%使った伝統的なお酒や100mlのアウトドア向け日本酒、リキャップできるおしゃれな一合瓶などの革新的なお酒も製造しています。また、飯米としても評価の高い魚沼産コシヒカリを使った酒造りにも挑戦し、美味しい日本酒を造ることができました。酒蔵としては歴史が浅いですがだからこそ新しいことにチャレンジしていける酒蔵です。
DHC酒造

<DHC酒造>の前身となる<小黒酒造>は1908年に創業。新潟市の中心部から北東へ約10kmに位置する豊栄地域で、豊穣に恵まれながら100年以上に渡り地元で親しまれる日本酒をつくってきました。「淡麗辛口」の味わいが主流の新潟県において、①うま味、②薫り、③後味が爽やか、④キレの4要素を大切に日本酒を醸しています。
私たちが目指す酒造りは、「人の手を掛ける酒造り」。市販商品においては2回火入れ(加熱殺菌)・タンク貯蔵の酒蔵が多いなか、高級酒クラスの鮮度管理を一般市販酒にも用いています。品質保持のための火入れは、高温により味・香り・風味を損なうデメリットもあるため、2回ではなく1回火入れを採用。貯蔵においては従来の冷蔵タンク貯蔵を廃止し、瓶詰め後の氷温貯蔵を行うなど、しぼりたての贅沢な美味しさを最大限お客さまにお届けできるよう努めています。酒造りに持てる気持ちの全てを投じる、そんな酒蔵であることを目指します。
中川酒造

当蔵は恵まれた自然環境のもと西山連峰から流れる伏流水と高精米する良質な新潟県産米を使い、手間を惜しまない高い技術と若い蔵人の和をもって、料理の邪魔をせず飲みあきのしないきれいな酒を造り続けております。
越乃白雁ブランドは地元消費率約70%の、ほぼ地元オンリーの蔵元です。
そのため、県外・海外に出回っている数量は極めて少なくなっております。
碧く光る地下水を使い、新潟県産米を高精白した米を使って美酒造りに励んでおります。
新潟銘醸

当社は新潟県のほぼ中央に位置する小千谷市にあります。
豪雪地として知られ、国魚に認定された色鮮やかな錦鯉を育む自然環境は酒造りにも適しており、魚沼西山水系を水源とする伏流水(軟水)を使用し、越後杜氏が厳冬期に精魂込めて醸しています。
新潟清酒の特徴である淡麗辛口とは一線を画す、まろやかな旨味と穏やかな香りのある「食と共にある日本酒造り」をモットーに、高品質かつ安全な酒造りを目指してISO9001を取得し、「美味しい」の先にある価値づくりに取り組んでいます。
白龍酒造

創業は1839年。蔵のある新潟県阿賀野市は、県都新潟市から南東におよそ20㎞、越後平野の中心部にあります。南側には、一級河川・阿賀野川が流れ、東側には標高1,000メートル級の山々が連なる五頭連峰がそびえ、麓には五頭温泉郷があります。冬には、2008年(平成20年)にラムサール条約で登録湿地となった「瓢湖(ひょうこ)」にシベリアから5,000羽あまりの白鳥が降り立つ自然豊かな地域にあります。
酒造りには主に契約栽培した『五百万石』を使用し、20余年前に地元農家、旧JA北蒲みなみとともに設立した『酒米協議会』のメンバーで栽培しています。毎年三者で協議を重ね、酒米の品質向上を図っており、現在では『越淡麗』を手掛けるなど、より高い品質を求めて活動を続けております。
蔵と同じ風土で育まれた米で醸す『白龍』の酒には米どころ阿賀野市の魅力と生産者の誇りが存分につまっています。
原酒造

柏崎の天地の恵みを酒に託して210年、伝統と歴史を醸す「越の誉」
海の街、新潟県柏崎市で1814年創業。
雪積り、水清く米どころと、豊かな自然な恵みを受け、越後杜氏が伝承の技で醸す。幾度の天災に見舞われながらもそれを乗り越えてきた蔵の歴史、「越後の誉れ高き名酒たれ」を礎に、地元を始め多くの人々に愛され、親しまれ、誇りにして頂いている事にお応えしていく、高品質な地酒づくりを目指し日々取り組んでいます。
峰乃白梅酒造

新潟から繊細な「蔵フトマンシップ-Kuraftsmanship」を世界へ
越後平野にある角田山の麓で約400年の‘’古い‘’歴史と共に酒を醸す蔵です。
かつて江戸時代には、コメ100俵の救済米を贈ったいわゆる「米百俵」の逸話でも知られている越後三根山藩に酒を献上し、平成の時代に入ってから「越後の三梅」と謳われ、地酒ブームを盛りあげていました。
この数年は飲み手の日本酒離れの波を押し返すべく、淡麗辛口タイプの酒質が多い新潟の地であえて、芳醇旨口タイプを軸として‘’新しい‘’日本酒造りに挑戦しています。
峰乃白梅純米吟醸は サケコンペティション2023でゴールド賞とJAL賞を受賞してJALのファーストクラスで提供されました。
また純米酒はサケコンペティション2024で新潟県内唯一ゴールド賞を受賞したお酒です。
雄大な平野と山や海などの自然の中で 昔ながらの方法と新しい技術で酒を醸しています。
妙高酒造

創業1815年(文化12年)200年を超える伝統を土台に、厳選された原料と創意工夫に満ちた酒造りの思想で個性豊かな酒を生み出します。酒造りの大きな要素である仕込み水には特に神経を使っており、軟水の妙高山系伏流水を使用、酒を口に含んだ時の柔らかさはここから生まれます。自社活性培養酵母を用いた二段酵母仕込み(1つの酒母に2つの酵母を使用)で、深みがあり飽きのこない酒を生み出します。
県内でも有数の米どころ頸城平野は清らかな水が上質な米を育て、冬は雪深く気温も低い、酒造りに最適な土地柄です。
杜氏平田正行は酒造りを志し20代で妙高酒造に入り38才の若さで杜氏となり以後約40年、妙高酒造一筋に妥協を許さず越後杜氏伝統の技で自身理想の酒を目指して醸し続けています。 平成21年には『にいがたの名工』22年には『全国技能士連合会酒造マイスター』に認定、両認定を受けた 新潟県初の杜氏となりました。
弥彦酒造

越後一宮・彌彦神社の御神体は弥彦山。その伏流水は超軟水、やわらかな酒を醸します。その伏流水が湧く山麓の「泉」と呼ばれる土地に、弥彦酒造は開かれました。幕末に確立された「泉流醸造法」を伝承し、少数精鋭で謹醸しております。神社に仕える御神酒蔵として、奇抜な酒は醸さず、多くの石数を造らず小仕込みで「本物の國酒」を追求し続けております。
代々菊醸造

米山と妙高山を眺望する田園地帯に位置し、大変に風光明媚な自然の中にあります。
尾神岳の伏流水と自作田で収穫した米、そして無心に蔵人が仕込む酒は、その美味しさから地元をはじめ多くの人達に愛されています。
新潟県にあっても、とても小さい酒蔵ですが、空気と水の美味しい環境の中で生まれる飲み心地の良いお酒「吟田川」をぜひ味わってみてください。
※数量に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。
※画像はすべてイメージです。
※20歳未満の方、お車・オートバイ等を運転される方の飲酒はご遠慮いただいております。
OTHER NEWS
その他のニュース